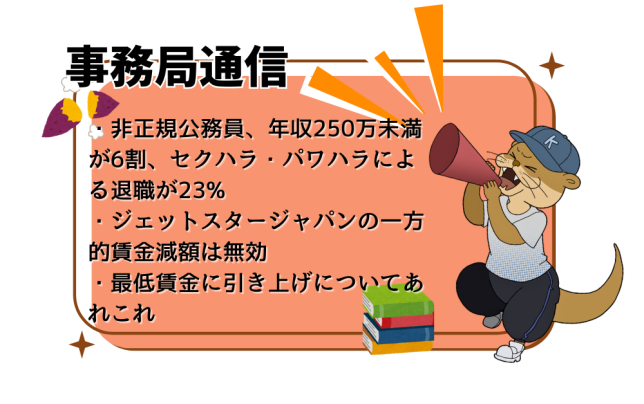目次
闘い
1.非正規公務員、年収250万未満が6割、セクハラ・パワハラによる退職が23%
9月9日、公務非正規女性全国ネットワーク(はむねっと)が、非正規公務職員の実態調査を発表した。5月~6月にかけて行われたもので、国や自治体の非正規職員480人が回答。担っている職務は「正規職員に仕事を教えている」(26%)、「決裁書を起案している」(25%)、「人材育成」(20%)など、正規と同じ仕事をしている人がたくさんいる。週あたりの労働時間は58%が30時間以上で、勤続年数が6年以上の人が42%に上るが、年収250万未満が6割を占める。退職者の23%がパワハラセクハラを理由に辞めている。
2.ジェットスタージャパンの一方的賃金減額は無効(9/11東京地裁判決)
格安航空会社のジェットスター・ジャパンの客室乗務員らが同社に対し、一方的に賃金を減額したのは違法だとして、未払い賃金の支払いを求めていた訴訟で、東京地裁は原告15人の主張を全面的に認めて、計約1212万円の支払いを命じた。最高裁は原告らの、2.9~10.8%の減額は「相応の不利益」であり、労働組合と実質的な交渉をしなかったことは「労働者の意見集約を怠った」と批判。会社は職責と業務内容に応じた処遇や公平性を考慮したものだと主張したが、裁判所は「高度な必要性や合理性は認められない」とした。
情報
1.最低賃金に引き上げについてあれこれ(さまざまな立場から)
7月に日米関税交渉で動き回っていた赤沢亮正経済再生担当相は、賃金向上担当相として最低賃金を巡っても「異例」の動きをみせた。国の審議会のとりまとめである厚生労働省が7月20日に、5%台を示したが赤沢氏は一蹴。厚労省は6%まで引き上げる案を示した。赤沢氏はそれでも納得せず、8月1日には経済団体幹部と面会して大幅引き上げに理解を求めた。国の審議会は8月4日に全国平均で63%、引き上げ率は過去最高の6%になった。赤沢氏はこれでも不満で、8月上旬の訪米中に「5、6人の知事に電話をかけて働きかけをお願いした」という。さらに8月14日、19日には福岡、愛知両県の知事を訪ねて「全国平均引き上げのけん引役」として目安を上回る引き上げを求めた。福岡は8月20日に目安を2円上回る65円の引き上げを労働局に答申した。自民党内からも批判の声も出ており、政府内でもやり過ぎという意見もあるが、赤沢氏は「政治生命をかけてやっている」という。
ニッセイ基礎研究所の久我尚子氏は、家計調査を見ると地方は「交通・通信」費や「光熱・水道」の支出額が大きく、「地理的条件により、『地方=安い』とは言い切れない」と指摘する。山梨県の長崎幸太郎知事は、「明確な賃金格差が、若年層を中心とする人材流出の要因の一つになっている」と積極的な引き上げ論を語った。同県の24年度の最低賃金は時給988円で、東京、埼玉、神奈川、長野、静岡に囲まれ、県境を接する4都県が時給1000円を超えており、最も近い県の長野も山梨より10円高い。支払い能力を超えた人件費を強いられれば経営は行き詰る。岩手の審議会では79円の引き上げが決まったが、使用者側は強く反発し採決を退席した。東京商工リサーチの原田三寛情報部長は「人材確保のための無理な賃上げは資金繰りに直結する。最低賃金倒産も懸念される」と指摘。
日経新聞は9月11日の社説で「最低賃金引き上げを続けられる環境作れ」と論じる。近隣県に負けまいと知事が地方審議会に要請して、人材流出を防ぎたいという危機感は理解できる。一方で引き上げの発効日を遅らせるのは企業側の準備期間を考慮したと言うが、大幅に遅れるのは極力避けるべきだ。より精緻なデータに基づいた決定方法へ改革する必要がある。審議を始める時期を例年の6月下旬から前倒しできないか検討の余地はある。企業の生産性向上が大前提であるが、政府は中小企業の投資を後押しする補助金の拡充に加え、労務費の価格転嫁が円滑に進むように監視を強める必要がある。2020年代に全国平均1500円の政府目標を達成するためには、政治家が口出しするだけでは実現は難しいと肝に銘ずべきだ。
経済産業省は9月9日、中小企業向けの「ものづくり」「IT導入」「省力化投資」の補助金の支給要件を見直すと発表。補助率を2分の1から3分の2に引き上げている特例要件を、今までは「地域別最低賃金プラス50円以内」の従業員が3割以上であることが条件だったが、今後は「改定後の地域別最低賃金未満」の従業員が3割以上を条件とする。
最低賃金をめぐる闘いはまだまだ続きます!!
(文責 川本浩之)