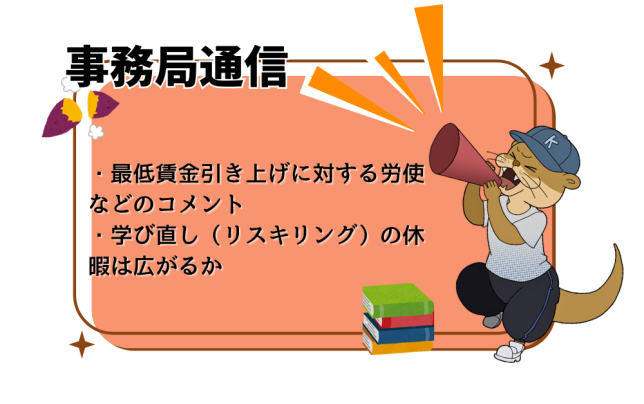目次
情報
1.最低賃金引き上げに対する労使などのコメント(10/6日経から)
中小企業家同友会全国協議会会長の広浜泰久氏(東京都墨田区の缶パーツメーカーヒロハマ会長)。最低賃金の引き上げは、大手に比べて中小のダメージがはるかに大きい。ただ、賃金引き上げの必要性は中小経営者も認識しており、政府は賃上げしやすくなる環境整備に取り組んでほしい。最賃1500円について、「対応不可能」や「困難」と答えた企業が4割、「対応済み」や「対応可能」の企業も4割で、二極化している。サプライチェーン末端の下請け程厳しい。下請法改正などで法令順守に敏感な大手は価格転嫁に応じるようになったが、中堅以下の発注者は対応が遅れているので、政府もしっかり後押ししてほしい。賃上げを抑制するのは中小にとって破滅への道で、ピンチをチャンスにする経営者の意識改革も重要だ。
UAゼンセン会長の永島智子氏。同労組の組合員の6割がパートやアルバイトなど短時間勤務労働者で、飲食業や小売業では最低賃金近傍で働く人も少なくない。貧困対策としても、短時間労働者の大きな割合を占める女性の処遇改善につながることも重要だ。特定の産業について地域別最賃より高い設定ができる「特定最賃」について、経営側の拒否感が強かったが、近年は地域の産業の魅力を高めるため、前向きな経営者も出てきた。サービスの対価を国が決めるため、賃上げなどの価格転嫁が難しい医療や介護などの業種はとくに特定最賃の活用が効果的だ。
山梨県知事の長崎幸太郎氏。最低賃金は地方の人口減少に直結する問題だ。これまでの最低賃金審議会は物価高で厳しい県民生活への責任を果たしておらず、なぜこんなに低いのか納得できる説明がない。倒産が増えて雇用が喪失するという意見はエビデンスに基づいていない。最低賃金を根拠づける詳細なデータがあれば、データを分析して賃上げにつながるより効果的な対策を打てる。県としても最賃の地域格差と人口流出の関連性など関係データを集めて分析し、審議会と共有していきたい。国が掲げる「2020年代に全国平均1500円」の水準は山梨にとって最低基準だ。
事務局通信で繰り返してきたことだが、中小企業労組による「地域的」あるいは「親会社・取引先」をも巻き込んだ、賃金引き上げの取り組みが必要不可欠だ。
1.「学び直し(リスキリング)の休暇は広がるか」(10/6日経から)
労働者がリスキリングのために連続30日以上の無給休暇を取得した場合に賃金の5~8割を受け取れる「教育訓練休暇給付金」制度が始まった。給付金の利用は就業規則で休暇制度が規定されていることが前提で、厚生労働省の24年度能力開発基本調査によると、教育訓練休暇制度を導入している企業は7.5%で、予定している企業9.1%と合わせても2割に満たない。導入予定のない理由としては、「代替要員の確保が困難」(46.3%)がトップを占める。阿部嘉一弁護士は「現時点では投資家の目を気にする一部の大手企業に限られており、スキルアップを支援しても転職してしまうのではないかと懸念する企業もある」という。上記調査で労働者に自己啓発における問題点を聞いたところ、正社員では「仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない」(55.9%)がトップ。
教育訓練休暇制度や給付金もあった方がよいに決まっているが、まずは年次有給休暇を完全取得できるような職場づくりや、教育訓練や病気の有給特別休暇制度を実現することが労働組合の役割だ。
(文責 川本浩之)