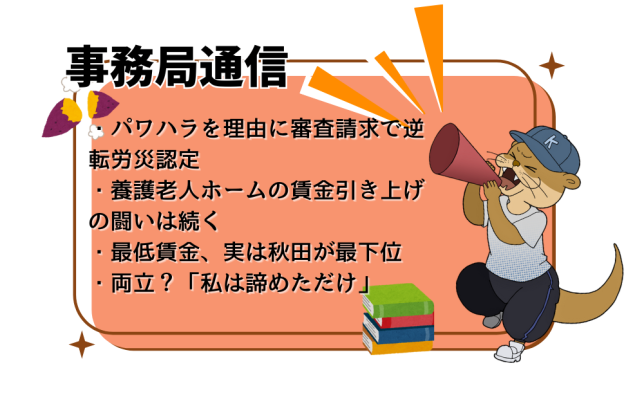目次
闘い
1.パワハラを理由に審査請求で逆転労災認定(スクラムユニオン・ひろしま)
2023年11月、ゲイソー・ロジスティクス株式会社古川浩延社長は、分会員に対して、長時間労働や隔離部屋の設置、パワハラ行為などを行った。その結果4名が精神疾患にり患し、3名が労災申請。2024年12月に2名が労災認定されたものの、1名(Aさん)が不支給、業務外となった。納得できないAさんは審査請求を行い、2025年9月に不支給処分取り消し、労災認定を勝ち取ったのである。
審査請求で精神疾患が逆転で労災認定されることは極めてまれで、例えば神奈川局では、昨年度は54件のうち業務上になったのはわずか1件。そして最も注目すべきなのはパワハラの心理的負荷を「強」としたこと。労働時間の場合は数字がはっきりするので、それだけで「強」となったり、パワハラ+労働時間が増えたことで認定されることが多い。先に認定された2人もそうであった。しかし、パワハラはけがをするほどの暴力や人格否定発言を繰り返すなどしないと、なかなか労災認定されることがない。あきらめずに闘ったAさん、支援したユニオンの画期的勝利だ。
1.養護老人ホームの賃金引き上げの闘いは続く(ユニオンおかやま)
Aさんは社会福祉法人が運営する養護老人ホーム(居宅で養護を受けることができない低所得世帯の高齢者が、自治体の「措置」により入所する施設)の有期雇用労働者。自分の賃金が低いことと、他の養護老人ホームの労働者との著しい賃金格差に疑問を感じてユニオンに加入した。ユニオンはAさんの賃上げと全職員の処遇改善を求めて団交を要求した。法人は、Aさんの賃金が最低賃金に抵触していたとして是正して解決。一方で他の養護老人ホームとの格差は、「民設・民営」と「公設・民営」によることが判明。ユニオンは瀬戸市に対して、老人保護措置費の増額を要請。市長選挙で新市長が誕生したことから8月20日に改めて要請を行った。
情報
1.最低賃金、実は秋田が最下位(9/19毎日など)
今年度の最低賃金が最低額となったのは、1023円の高知、宮崎、沖縄の3県。実際には少し違う。各地で発効時期を例年よりも大幅に遅らせる動きが広がり、2024年度は徳島県を除く46都道府県が10月中に発効したが、今年度は27府県が11月以降に設定した。とくに秋田、群馬、徳島など6県は2026年1月以降の発効で、最も遅いのが秋田県で3月31日。北海道大の安部由紀子教授が、25年10月1日から1年間の年収を計算したところ、最も低いのは秋田県の991円。続いて高知、沖縄県で1011円、熊本、福島県で1013円となる。この算出方法によると、10月から発効することを「前提」とした場合の国の目安額を1円以上下回るのは25府県に上る。秋田は80円引き上げたが、半年の先送りにより、実質は40円しか上がらず、目安を24円も下回る。最低賃金法では発効時期を規定しておらず、国の審議会が「発効日は地方で十分審議を」と報告書に盛り込んだことも遅れにつながった。和歌山県の審議会は「地方ごとに判断すべき問題ではなく、中央審議会において一定の方針を示していただきたい」と国に要請した。
1.両立?「私は諦めただけ」(9/17日経など)
少子化に歯止めがかからない。大手ゼネコンに勤める40代の女性は、第1子出産後も花形の設計部で活躍していたが、定時退社するようになり仕事が回らず、「うつ状態」と診断された。夫は家事や育児に協力的だが勤務時間を減らすわけではなく、平日は一人で育児せざるを得なかった。サポート部門に移り、昇進もしたが、「私は最前線に残るのを諦めただけ」と言いたくなると語る。
慶応大学の寺井公子教授は「長時間労働を前提とする正社員制度の下で両立できるのは『スーパーウーマン』だけだ」と指摘。スーパーウーマンになれない女性は重要なポストや就労自体を諦めざるを得ない。少しずつ上昇しつつあるとはいえ、2015~19年の第1子出生後の就業継続率は69.5%(国の「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会の2025年5月の資料から、なぜか5年前のデータ)であり、なお3割の女性が出産を機に退職する。これまでの両立支援は女性の就労を促すことが主眼で、男性を中心とした長時間労働の是正は十分に進まなかった。残業割増率が低いことも企業が残業ではなくて新規に労働者を雇う方向に向かわないことも以前から指摘されている。
厚生労働省によると、既存の従業員に残業させる場合と新たに採用する場合の人件費を比べた「均衡割増賃金率」は21年に44.3%。つまり割増賃金率がこれよりも高ければ企業は新規で雇った方が人件費は抑えられて、残業の抑制につながる。高知県では職員の割増賃金率を実験的に25%から50%に引き上げる条例案を県議会に提出すると発表。成立すれば自治体で初めてとなる。
ちなみに現在開かれている労働政策審議会では、もっと働きたい人がいる、裁量労働制を拡大すべきだなどと使用者側の委員が主張している。働き方改革、労働時間規制に逆行する動きであり、女性はもとより、労働者の健康や生活、社会全体のことなど何も考えていないと言わざるを得ない。
(文責 川本浩之)