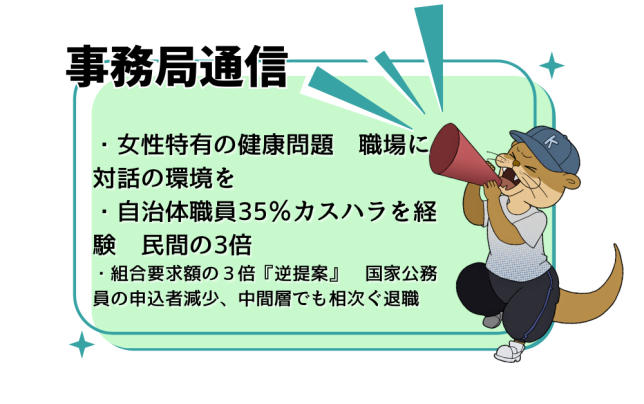目次
情報
1.「女性特有の健康問題 職場に対話の環境を(産業医科大教授 立石清一郎氏)」(4/27毎日から)
戦後日本の労働安全衛生対策は1947年に制定された労働基準法がベースで、夜勤のある工場労働や残業が当たり前といった男性中心の社会の仕組みの中で考えられたもの。政府は女性活躍推進を取り上げるが、職場は男性中心の仕組みが残っている。女性が健康課題を抱えていることを企業や管理職が認識して相談に乗る姿勢を明示し、本人が申し出やすい環境を作ることが基本だ。ただし企業が「女性のために必要だから」と一方的に制度を作ったり、方法論を押しつけたりするのはよくない。「女性は体が弱いから夜勤の回数を半分にする」など、一律にしてしまうと「半分しかできないのか」と感じる人もいるし、違う差別を生みかねない。国の労働政策審議会の分科会では、職場の健康診断の問診票に女性特有の健康課題に関する質問を加え、必要に応じて専門医への受診を促す案が了承された。導入は来年度以降になると思われるが、効果の検証も必要だ。質問は気づきにはなるかもしれないが、企業が申し出に対して必要なことを実践するのが本来の姿だと思う。健康課題を認知するため、月経などタブーにされがちだった話をオープンに議論できる環境が企業内はもちろん、学校など社会全体に広がることも期待される。
2.「自治体職員35%カスハラを経験 民間の3倍」(4/27各紙)
総務省は自治体職員を対象とした職場のハラスメントに関する初の実態調査結果を公表した。住民や業者から理不尽な要求を受けるカスタマーハラスメントを過去3年間で経験したと回答した割合は35.0%に上る。厚生労働省が昨年5月に公表した民間企業・団体を対象の実態調査では10.8%。総務省は、企業は顧客を選別できるが自治体では全ての利用者にサービスを提供する必要があることが影響しているのではないか」と分析。広報や広聴ではカスハラを経験したと回答する人は66.3%に上り、各種年金保険関係、福祉事務所もともに61.5%が経験したと答えた。
3.「組合要求額の3倍『逆提案』 国家公務員の申込者減少、中間層でも相次ぐ退職」(日経4/23から)
「うちも5万円ぐらいベア上げられへんか?」。2024年10月、日本曹達の人事部長が人事管掌役員に呼ばれて言われた。25年の春季労使交渉で同社は、基本給を一律5万円の賃上げを「逆提案」した。組合からの要求額の約3倍、定期昇給分を併せた賃上げ率は18.8%にのぼる。実は採用面接後に給与の説明をすると、「御社は業績連動の割合が多いですね」という理由で辞退されることがあった。初任給を上げれば採用活動は格段にやりやすくなる。
人材獲得に悩むのは民間に限らない。24年度の国家公務員総合職の採用試験の申込者は14年度と比べて2割減った。50代の経済産業省幹部は、「若手だけでなく課長や課長補佐などの中間層もベンチャーや待遇の良い子が医師のコンサルティングに流れている。政策、法律を書ける人材がどんどん減っていて、担当以外の業務もふられてきつい」と話す。危機感を持つ人事院は24年度の国家公務員の行政職の月給について、定期昇給分も含めて4.4%の給与改善を勧告したが、5%を超える賃上げを進める民間には見劣りする。人事院が25年3月に公表した有識者会議の最終提言では「あらゆる国家公務員の人材確保が危機的状況にある」と指摘し、大企業に準じて改善すべきだとした
(文責 川本浩之)