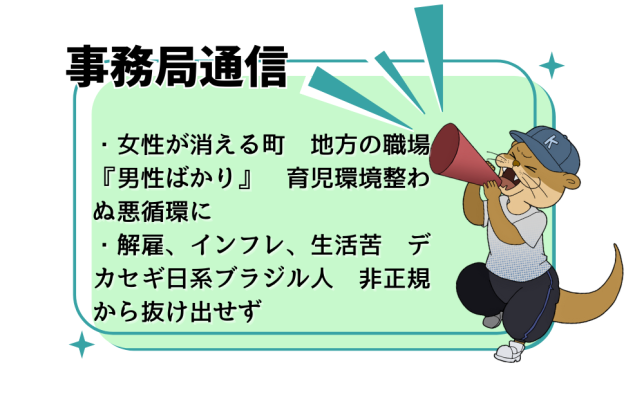目次
情報
「女性が消える町 地方の職場『男性ばかり』 育児環境整わぬ悪循環に」(3/25日経)
地方から女性の流出が止まらない。女性が働きやすい場所が少なく、出産・育児の環境も整わないほか、女性の地方議員が少なく意見が反映されにくいことも一因。
地方の女性の仕事の選択肢は限られており、非正規雇用も多い。24年の熊本県の女性の転出超過は男性の3倍、栃木県では2.9倍だった。栃木県は男性の賃金水準を100とした場合の女性の水準が71と男女間の格差が全国最大。出産適齢期の女性が流出した地方は人口の維持が難しくなる。子育てで親や家族のサポートを受けやすい利点はあるものの、根強く残る「子育ては女性が担うもの」という風土も女性を地方から遠ざける。ニッセイ基礎研究所の天野馨南子氏は「Z世代では男女ともに共働き希望が多く、女性だけではなく男性の東京流入も今後加速する」と話す。
23年末時点の全議員に占める女性の割合は町村議会で13.6%、都道府県議会では14.6%で、東京23区議会(36.2%)や政令指定都市の市議会(22.9%)とは差がある。東大の前田健太郎教授は、「日本の利益集団政治とは、男性の政治家や官僚に対して、男性の利益集団が圧力活動を行う過程だ」と、著書「女性のいない民主主義」で述べている。
「解雇、インフレ、生活苦 デカセギ日系ブラジル人 非正規から抜け出せず」(3/27毎日)
日本がバブル景気に沸いた頃、多くの日系ブラジル人が「デカセギ」で来日。それから30年余り、非正規雇用などの厳しい条件で働き続け、ここ数年の物価上昇に苦しむ人は少なくない。
生後5か月で両親とともにブラジルに移住した日系ブラジル人の群馬県大泉町に住む吉岡博さん(仮名 66歳)は、1989年に来日した。35年間に及ぶ日本生活の9割以上の期間を大泉町で暮らしてきた。同町は人口4万人あまりのうち外国人が約2割を占め、うち半数以上がブラジル人。吉岡さんも一時期は、自動車部品工場で正社員並みの待遇で月の手取りが35万円に達したこともあった。2006年にマイホームを建てて30年を超すローンを組んだが、08年のリーマンショックで失業すると、その後は徐々に賃金の低い職場に移るほかなかった。吉岡さんの手取りは現在16万~18万円程度。月に8万7000円のローン返済が重くのしかかる。「世間では給料が上がったというが、物価はもっと上がった。給料が下がった私はどうしたらいいのか。」
独立行政法人経済産業研究所の橋本由紀上席研究員が、国勢調査のデータを集計したところ、在留ブラジル人のうち専門的・技術的職業で正社員として働く割合は、2010年の時点で4.6%。10年後の20年も5.9%にとどまっていた。さらに管理的職業に従事する正社員は0.2%のままと極めて小さい。「正社員の専門職や管理職になれないわけではないが、とても細いルートで多くはブルーカラーから抜け出せない状況に陥っている」と語る。大泉町の隣の群馬県太田市で広告代理店を営む日系3世の平野勇パウロさんは、「近隣の工場では非正規で働く日本人の高齢者もたくさんいる。将来への不安は日系人社会独特の課題でなく多くの人々がぶつかっている問題だ」と感じている。待遇が不安定で、長年、安価な労働力として都合よく使われてきた人たちの高齢化が進む。
(文責 川本浩之)